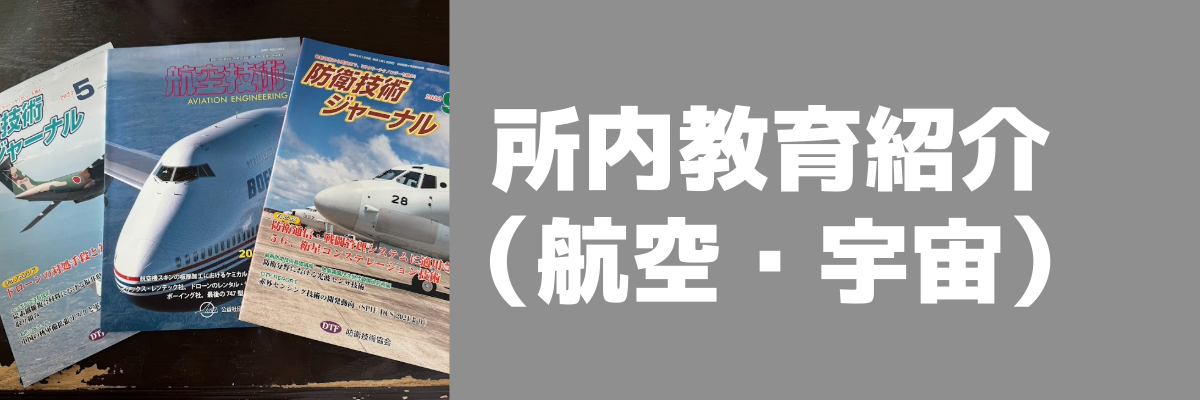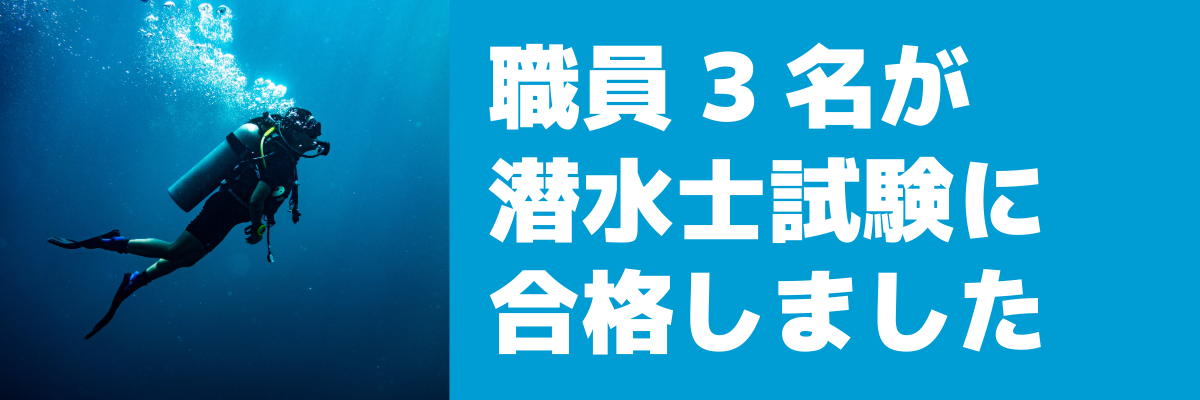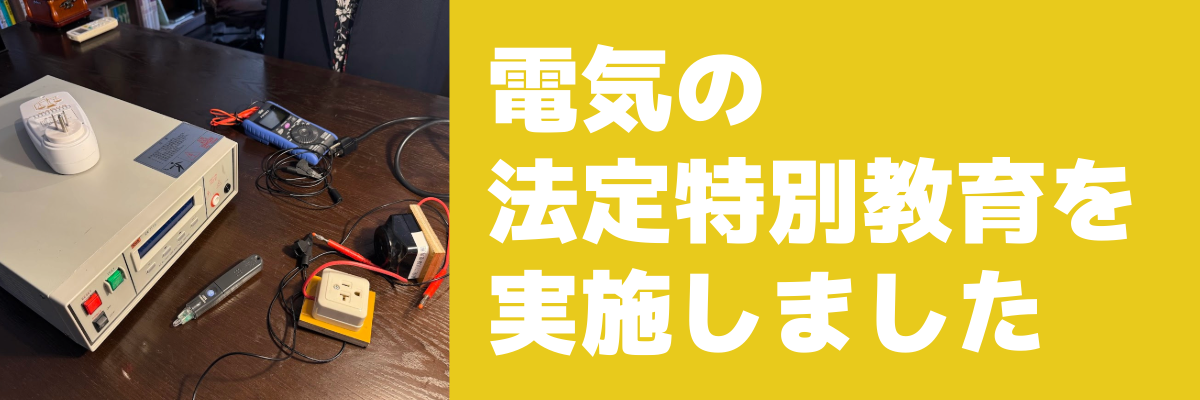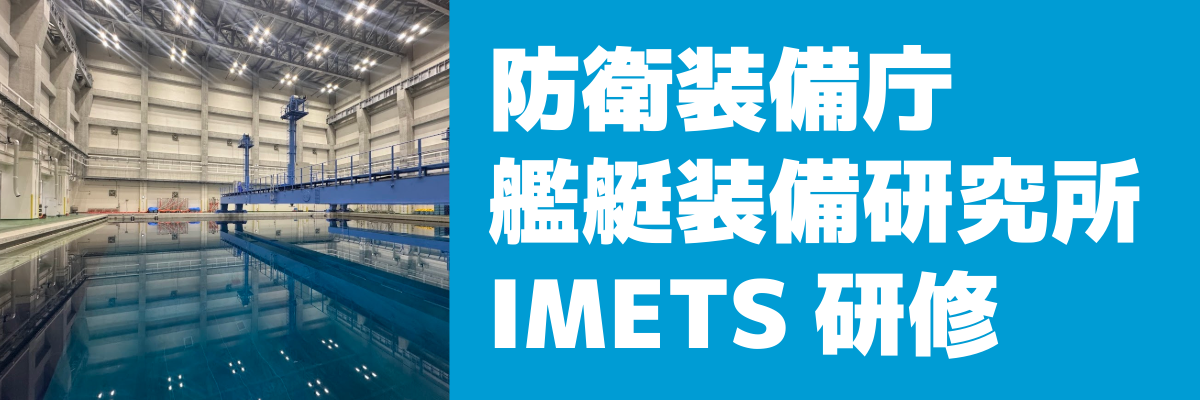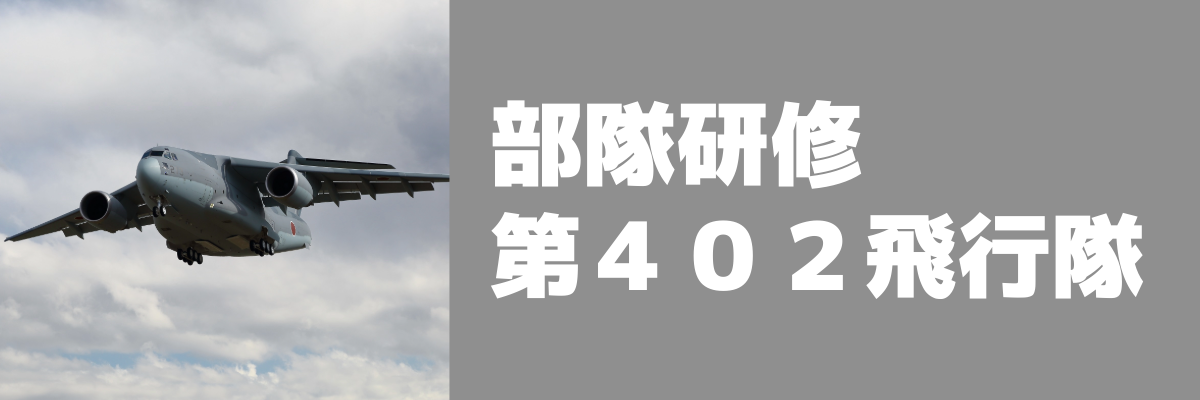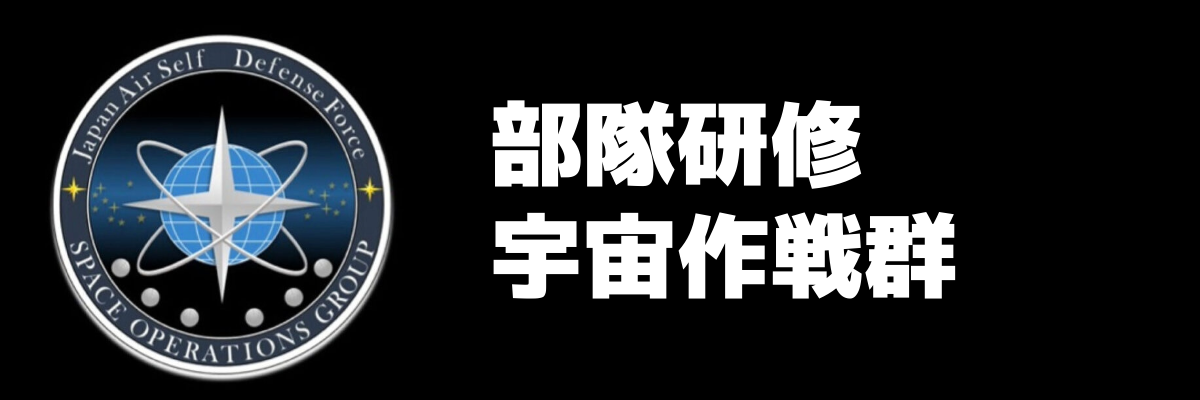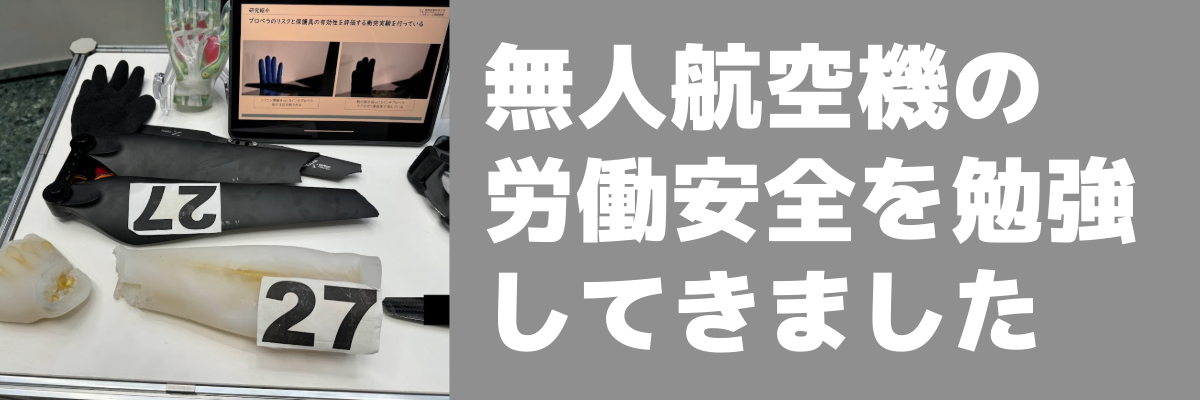行政書士法人メイガス国際法務事務所
所内教育研修と法技一系化
行政書士法人メイガス国際法務事務所では、所内教育・職員研修を重視しており、法務サービスの品質保証を支える不可欠な基盤と位置づけています。
特に、弊所が扱うサービスは、外為法、電波法、電安法といった、技術的知識と法的知識の双方の理解が不可欠な領域です。これらの実務では、法令文を読んでも技術的知識がなければ法制度の理解が難しいため、製品知識や技術的常識を踏まえて法令を調査し、実際の製品や技術にあてはめて理解する必要があります。
例えば、「航空機用のリングレーザージャイロを輸出したいので該非判定(輸出したい貨物が外為法の輸出規制の対象となるか否かを判定する作業)をしてほしい」とクライアント様からご相談を受けた場合、まずリングレーザージャイロとはどういう貨物で、どういう原理で動いているのか知っていないと、適切なヒヤリングができません。さらに、外為法ではリングレーザージャイロを輸出する場合、「角度のランダムウォーク」や「バイアス安定性」といった性能によっては輸出規制に該当し、経済産業省の許可がないと輸出できないと書かれてありますが、ここでも技術的知識が必要となります。そのため、リングレーザージャイロの仕様書を読み込んだり性能グラフを読図して、それらの性能値を見つけ出し、該非判定を行う必要があります。
弊所職員はこのような案件にいつでも対応できるように、所内教育として「外為法」だけでなく「光学」や「航空工学」が用意されており、「サニャック効果(リングレーザージャイロの動作原理)」や「バイアス安定性とバイアス再現性の違い」など、技術的な内容についてもしっかりと教育を受けています。
このように、弊所では日頃から法制度に加えて関連技術についても基礎から教育を行い、法令と技術を行き来できる職員の育成に努めております。そのため、弊所では法務系職員と技術系職員をわけて採用することはありません。法律系(文系)のバックグラウンドを持って弊所に入職した職員は、技術系(理系)の教育研修を集中的に受講する必要がありますし、逆も然りです。
弊所ではこれを「法技一系化」と称し、理系・文系問わず全職員に法務系・技術系の教育を行い、法務・技術間での情報断絶を防ぐ運用を徹底しています。法令知識・技術知識のいずれかが不足する職員による法令誤解・誤判定・申請ミスといったトラブルは、クライアント様に大きな時間的・金銭的損失をもたらしかねません。私たちはそのような法務過誤を起こさない体制づくりが、誠実なサービスの提供のために不可欠であると考えています。
法技一系化がクライアント様へ還元する価値
1. 外為法や電安法等の対象/非対象の誤判定防止
クライアント様の製品について、各種法令対応要否についての誤判定/誤判断を防ぐために、法律上の取り扱いがグレーな製品や、製品知識や技術常識がないと判断を誤る複雑な製品などを題材に、正しく判定する教育を実施しています。
2. 意見表明までのリードタイム短縮
法令・技術の両分野の教育を受けた職員による適切な判定により、ご相談への回答・意見表明の時間が短縮できます。
弊所では海洋分野の案件は、海洋関係の国家資格(海事代理士、潜水士、海上無線技士等)を持つ行政書士が担当したり、半導体分野の案件は世界的な半導体素子メーカーの元エンジニアとしての経歴を持つ行政書士が担当するなど、業界・製品に関する基礎知識を有する職員が案件を担当しています。それにより、技術的常識や前提知識を持たない職員が担当するよりも迅速にご相談への回答・意見表明ができます。
3. 実務提案力の向上
単に「製品が法令に適合しているか判断する」だけではなく「どうすれば製品が法令に適合するか」を検討して提示するためにも、法令・技術の両分野の教育が必要です。例えば海外製のAC/DCアダプターを国内で輸入販売する際、PSEに対応させるためにトランスやコイルを交換するか、それとも取扱説明書の記載を修正するだけで済むか等を検討するためには、経産省の電気用品安全法関連の通達や内規を読み込む必要がありますが、これにも法令・技術の両分野の知識が必要です。
4. 法務・技術間の情報断絶の防止
外為法、電気用品安全法、電波法などの技術系の知識が要求される法令については、行政書士とエンジニアが協同する形態も考えられますが、弊所ではそのような運用はされておりません。理由としては、技術知識が足りない行政書士と、法令知識が足りないエンジニアの間で誤解が発生しても、相互に気づくことができないためです。
例えば、「この無線機を輸出したいが外為法で規制されていないか調べて欲しい」という相談があった場合、行政書士が外為法令を読んで「無線技術はよくわからないけれど、スペクトラム拡散通信ができる無線機は規制されているらしいです。この無線機はどうですか?」とエンジニアに尋ねることになります。エンジニアとしては「DSSSのことですよね?(FHSS機能は搭載されているけど)DSSSはこの無線機は関係ないですよ」と答え、行政書士が「それなら良かった。輸出規制に非該当ですね」と判定したとします。しかし、これは誤判定です。
この事例での落とし穴は、実は法令で規制されているスペクトラム拡散通信(SS)には、DSSS(直接拡散)とFHSS(周波数ホッピング)の両方が含まれていた、ということです。この事例はあくまでも簡単な仮定で、防ぎようも色々とあったと思われますが、重要なポイントは、似たような失敗は他にもいくらでも起こり得るということです。また、今回の事例では行政書士に技術的知識がないことによる過誤事例でしたが、反対に技術者に法的知識がないことによる過誤事例も考えられます(例えば不適切な類推解釈や、判例の射程に関する誤解等)。
このような過誤を防ぐため、弊所では技術者と行政書士をわけず、理系出身の技術者には行政書士資格を取らせ、文系出身の行政書士には様々な技術者資格(例えば電気主任技術者、高度情報処理技術者等)を取らせたり、所内教育を受講させたり、大学や専門学校へ学生として派遣したりと、様々な教育面での手当により、法技一系化を実現しています。
弊所職員による教育関連のコラム記事は下の画像をクリック(リンク先は弊所のリクルートサイトです)
所内教育に関するコラム
外部派遣教育・外部研修に関するコラム